✅メリット(働く側)
- 店舗維持費・人件費が抑えられる
→ 個人経営の場合、大規模な会館やスタッフを抱える必要がなく、経費が少なく済む。 - 葬儀費用の利益が多く残る
→ 固定費が少ないため、1件ごとの利益率が高くなる傾向がある。 - 料金設定を柔軟にできる
→ 依頼者の希望や予算に合わせて自由にプランや価格を調整できる。 - 地域密着のサービスを提供しやすい
→ 顧客との距離が近く、口コミや紹介で信頼を得やすい。 - 自分の理念を反映した葬儀ができる
→ 大手では難しい、心のこもった小規模で温かい葬儀スタイルを実現できる。 - 働く時間・仕事量を自分で調整できる
→ 家族経営や副業的な形も可能で、働き方に柔軟性がある。
⚠️デメリット(働く側)
- 24時間対応などで拘束時間が長くなりがち
→ 個人経営では交代要員がいないため、夜間対応や急な依頼にも自分で対応する必要がある。 - 営業・集客の負担が大きい
→ 大手のような広告力がなく、口コミや紹介に頼るため、安定した依頼を得るまで時間がかかる。 - 設備や在庫への初期投資が必要
→ 霊柩車・式具・保管設備などを最低限そろえる必要がある。 - 社会的信用・認知度が低い場合がある
→ 個人葬儀社は「ちゃんと対応してもらえるのか」と不安に思われることも。 - 法令・手続きに関する知識が不可欠
→ 死亡届、火葬許可、遺体搬送、宗教儀礼など、多岐にわたる知識と対応力が求められる。 - 精神的な負担が大きい
→ 常に「死」と向き合う仕事のため、心のケアが必要になることも。 - 人的資本(スキル・人脈・信頼)が必要
→ 葬儀業は専門知識だけでなく、僧侶や火葬場、花屋など地域関係者とのつながりが重要。
また、遺族対応やマナーなど人間力が問われるため、個人の力量が業績に直結する。
まとめ:個人で葬儀屋をするのに向いている人・向かない人
🌿向いている人
個人で葬儀業を行うには、地域とのつながりや人との信頼関係が何よりも重要です。
そのため、次のような人が特に向いています。
- 地域の交流が多く、人のためにを常に考えられる人
→ 地域社会の中で人の役に立つことに喜びを感じられる人は、自然と信頼を得やすい。 - 信用貯金(人からの信頼)がある人
→ 人生の節目を任せてもらうには、「あの人なら安心」という信頼感が欠かせない。 - 顔が広く、地域の人脈がある人
→ 僧侶・花屋・火葬場などとのつながりが、スムーズな葬儀運営につながる。 - 誰にでも合わせられる柔軟な対応力がある人
→ 遺族の悲しみや宗派・価値観に寄り添い、丁寧な対応ができる人は重宝される。
⚠️向いていない人
一方で、以下のような特徴がある人は、個人での葬儀業には向いていない傾向があります。
- これまで葬儀に出た経験がない人
→ 実際の流れや儀礼の雰囲気を知らずに始めると、現場対応に戸惑いやすい。 - 人の死に直面したことがなく、感情の整理が難しい人
→ 遺族の前で冷静に対応できないと、信頼を損なうおそれがある。 - 地域での認知度が低い人
→ 個人葬儀社は知名度や口コミが生命線。信頼の「入口」がつくりにくい。 - 人との交流が苦手な人
→ 葬儀は“人のつながり”で成り立つ仕事。挨拶・会話・営業活動が苦手だと継続が難しい。
このように、「人との関係づくり」と「信頼」が核になる仕事であるため、
「地域のために」「誰かの役に立ちたい」という気持ちを強く持てる人ほど成功しやすいと言えます。

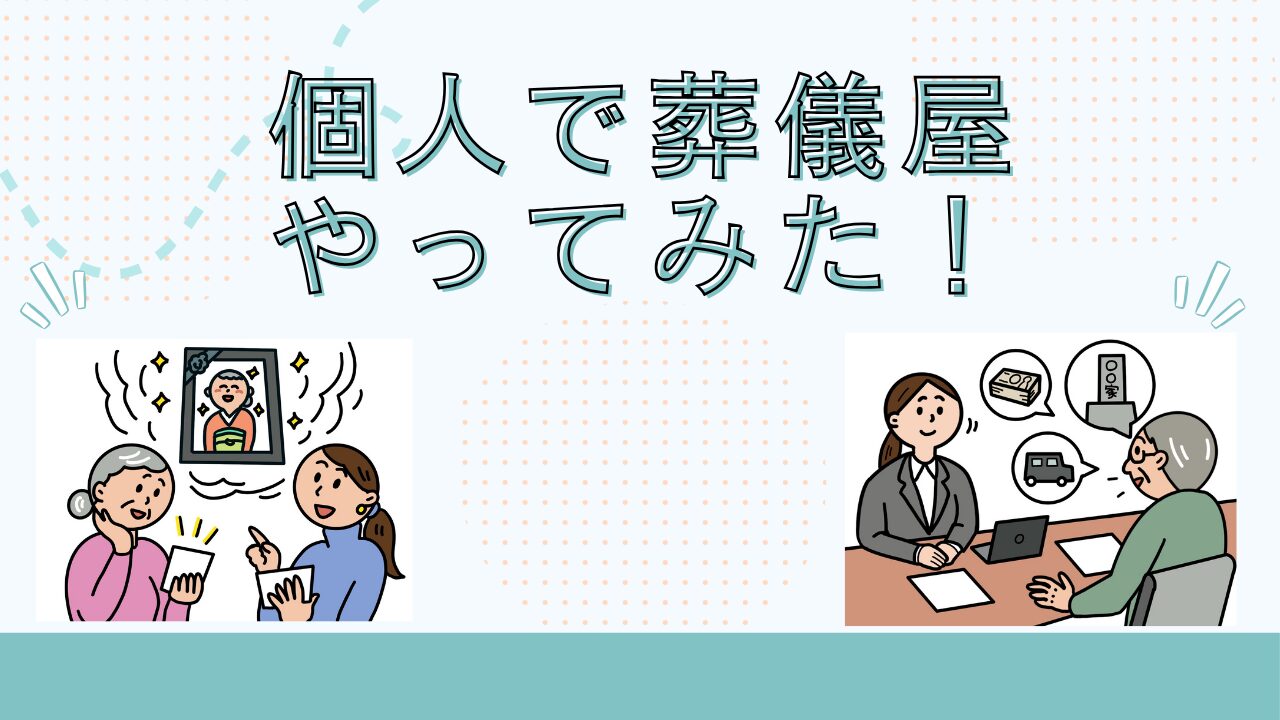


コメント